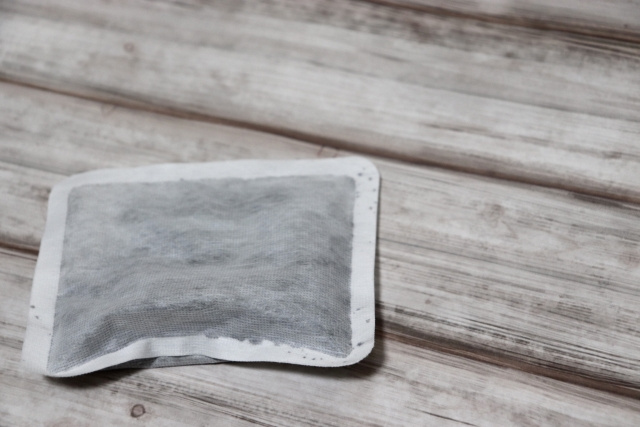2023年の4月中旬、佐渡島南部の山奥にある友人のおばあちゃん宅を友人親子と訪ねた。
2023年の4月中旬、佐渡島南部の山奥にある友人のおばあちゃん宅を友人親子と訪ねた。
90歳になったおばあちゃんの家のすぐ裏にある里山へ、この季節の日課である山菜狩りに同行させていただくためだ。
里山という言葉はよく聞くし、概念としては何となくわかるのだが、そこに実際訪れるのは初めてかもしれない。
 しばらく里山を登っていくと、そこそこ急な斜面をおばあちゃんがスルスルと降りて行った。
しばらく里山を登っていくと、そこそこ急な斜面をおばあちゃんがスルスルと降りて行った。
ここは日当たりの悪い側の土地で、水分を好むコゴミ(クサソテツ)がたくさん生えているそうだ。
 コゴミを摘んだその先には、日当たりの良い斜面に太くてしっかりとしたワラビがたくさん生えていた。
コゴミを摘んだその先には、日当たりの良い斜面に太くてしっかりとしたワラビがたくさん生えていた。
採り切れないほどのワラビ。これぞ長い冬を越えて大地から湧き上がる里山の恵みである。
 いろいろな山菜を採らせてもらったが、その中でも今回の目的はゼンマイである。
いろいろな山菜を採らせてもらったが、その中でも今回の目的はゼンマイである。
これまで何度も見かけていたのだが、コゴミやワラビのようにすぐ食べられる山菜ではないらしいのでスルーしていた。だがせっかくの機会なので、おばあちゃんに処理の仕方を教えてもらって、伝統の食文化に挑戦してみたいと思う。
 手間暇をかけてゼンマイを食べるという行為に、前からとても憧れていたのだ。
手間暇をかけてゼンマイを食べるという行為に、前からとても憧れていたのだ。
さて本題のゼンマイである。
おばあちゃんに教わったことを思い出しながら、保存食として加工してみよう。
 こうして茹でたゼンマイを干して揉んでいくのだが、ここで私は大きな勘違いをしていた。
こうして茹でたゼンマイを干して揉んでいくのだが、ここで私は大きな勘違いをしていた。
これまでメンマ用タケノコなどを干してきた経験から、数日経ってほどほどに乾いた状態で揉むのだろうと思っていたが、どうやら干した日から数時間ごとに揉むのが正解だったようだ。
 うっかり3日ほど干してしまったところ、ゼンマイはマッチ棒の燃えカスのような細さになっていた。
うっかり3日ほど干してしまったところ、ゼンマイはマッチ棒の燃えカスのような細さになっていた。
触ってみるとカッチカチ。揉んだ瞬間パキパキに割れそうである。ゼンマイってこんなに乾きやすい植物だったのか。
まったく保存に向かない形状になってしまった。揉むという行為は繊維をほぐして柔らかくするということ以上に、保存食として収納しやすくするという意味があるのかもしれない。
出典:DailyPortal